
団野法律事務所
介護事業所・放課後デイ・障害者福祉施設の行政110番「実地指導、監査、聴聞、連座制など 行政対策専門弁護士」
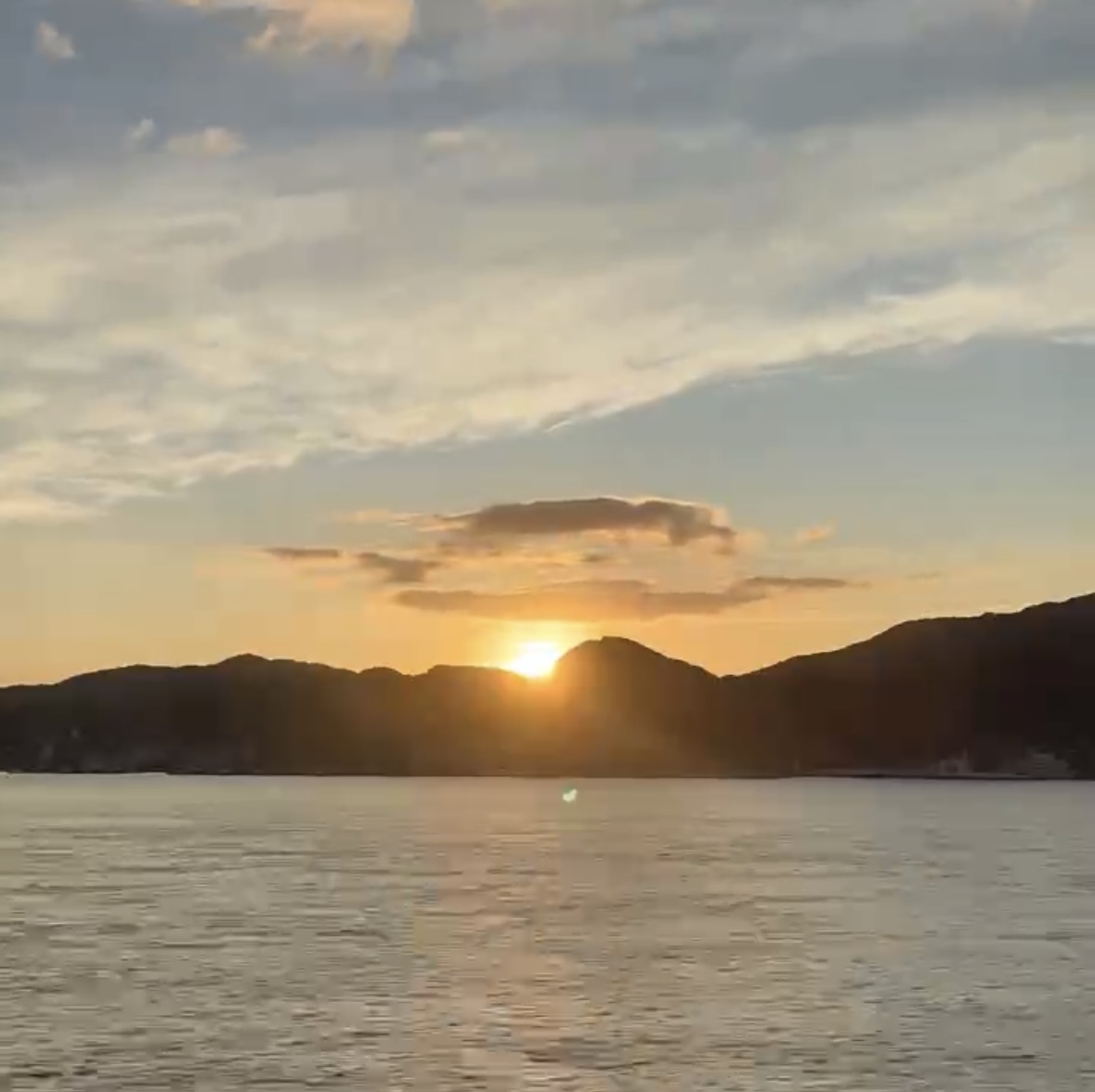
謹賀新年
福祉を取り巻く環境が大きく動く中、
現場の努力と工夫がますます重要な時代となっております。
本年も、法令遵守はもちろんのこと、行政対応・法務の側面から全力でサポートを行い、事業所の皆様が前向きな一歩を踏み出すための「実務に役立つ法務支援」をお届けできれば幸いです。
皆様のご発展と現場のさらなる前進を心より応援しております。
団野法律事務所 弁護士 団野克己
TEL0952-29-5036
福祉事業所を運営する中で、行政とのやり取りは避けて通れません。日々の業務において、法的なアドバイスやサポートは不可欠です。しかし、行政対応の煩雑さや、法律に関する専門的な知識不足は、大きなリスクとなり得ます。 ★そんな時こそ、行政対応に特化した弁護士があなたをサポートします! 【なぜ、福祉事業所に行政対応弁護士が必要なのか? 】 1、行政指導や監査への対応 …福祉事業所は、様々な行政の規制を遵守する必要があります。行政からの指導や監査は、事業の運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。違反等があれば、聴聞、処分(指定取消や効力の一部停止、過誤返戻など)とつながりかねません。 2、早めに適切な対応をすることで、リスクを最小限に抑えることができます。経験豊富な弁護士がいれば、迅速かつ的確な対応で、行政に対しても、利用者様にとっても事業の信頼を守ることができます。
行政対応弁護士がもたらす3つのメリット
・リスク管理の徹底:法律的なリスクを事前に見つけ、適切な対応策を講じることができます
・時間とコストの節約:行政調査、行政監査の段階、聴聞になる前にご相談いただくことで、以降に起こることを示し、ダメージを最小になるように解決に導きます。
・事業の信頼性向上:法律に基づいた運営を行うことで、行政からの信頼を得やすくなり、事業所の信用が向上します。
★行政の調査・監査・聴聞についてなぜ早めの相談が大事なのか?
それは、監査≒聴聞=行政処分だからです。
さらに聴聞⇒行政処分⇒過誤返戻⇒複数事業所営の場合⇒連座制適用⇒更新できなくなる場合があります
【監査とは?】
監査とは、公権力に基づく行政調査のことです。監査開始から10日以内に聴聞決定予定日の通知がとどくと、事業の廃止も制限されます。複数事業所を経営されている場合は,不用意な事業廃止については、連座制が適用される場合もあります。
【聴聞とは?】
聴聞手続は、事業者が質問・反撃が許される唯一の場です。聴聞手続で「どれだけ的確かつ正確に弁明ができたか」は、のちの行政訴訟の勝敗を分けることがあります。 早めの相談と、早期の弁護士対応が、聴聞を活用する条件です。
【過誤調整】
行政指導により,過去の報酬請求を任意にとりさげ,再請求するというものです。高額な過誤はめずらしくありません。過誤調整が本当に必要な場合か、そうでない場合の判断は、法令の正確な適応能力がためされます。非常に判断が難しいです。
法令違反があるようにみえると、過去の請求を任意に取り下げるように指導する地方自治体がありますが、適切な判断かどうか微妙なケースがありました。
指導にしたがわないことを、不利益処分の根拠とすることはできません。
素直に過誤指導に応じれば、処分がないというのは、まちがった認識です。
お知らせ1 監査聴聞救済センター新聞
お知らせ2 佐賀県行政書士会主催の「不服申立に関する業務研修会」で講師をします
行政書士の不服申立の代理権の範囲が拡大されました。それに伴い、九州の行政書士の先生方を対象に、不服申立制度を利用するための必要な知識の習得、実際の運用方法の確認を目的として 2 回に分けての研修講師をさせていただきます。その後OJTあり。
■ 内 容 「審査請求入門 〜業務拡大に向けて〜」
■ 日 時
【第 1 回】令和7年9月10日(水)13:30〜13:55
行政書士法改正についての解説
講師:佐賀会 德永 浩 相談役
14:00〜15ː30(約 90 分)
本編研修
講師:佐賀県弁護士会 弁護士 団野克己
【第 2 回】令和7年9月24日(水)14:00〜(約 90 分)
本編研修 講師:佐賀県弁護士会 弁護士 団野克己
■場所 佐賀市内、オンライン
お知らせ3 団野法律事務所電話無料相談
介護、福祉サービス事業者様、放課後デイ専用、電話で初回30分無料相談します。
調査、監査、聴聞対応、行政との交渉等
期間12月8日~12月26日まで
0952-29-5036までお気軽にお電話ください。

お知らせ4

「聴聞ってなんだ?~介護事業所、障害者福祉施設、放デイの聴聞対策マニュアル~」完成 Amazon楽天で注文受付中!
聴聞というのは、行政庁が事業者に対して重大な行政処分をおこなう際の事前手続です。建前としては憲法上の手続保障などいわれていますが、事業者からみれば、事業の妨害だから侵害行為だ、と感じるもの。
この本は、一般に公開されていない(福祉サービス事業者の)聴聞についての対策マニュアルです。
聴聞通知が届いてから、事業者が行政処分される前に考えられる対策を紹介します。
目次 1 聴聞とは謝る場ではない
2 聴聞は使い方を間違えなければすごい
3 聴聞通知が届いたぞぉ
4 なんで自分のところがこうなるの
5 事業所AとBに監査があり、A事業所に聴聞通知がきた。Bはどうなるの?
6 指定取消を受けるとどうなるの? 処分ってどんなものがあるのかな。
7 聴聞は誰が出頭するの?
8 聴聞の開始から終わりまでって本当はどうなっているの?
9 聴聞期日、当日の具体的な流れ
10 聴聞手続中、利用者へのサービス提供は続けてよいのか など
監査や聴聞では、法令に基づく反論は忖度せず正直にすべきです
このことを知っている法曹関係者は多くありません。行政に刃向かってはいけないというアドバイスが多いからです。情緒的・感情的に訴えても意味はありません。
聴聞に出席しない、または素直に謝ったとしても、間違いを認めたことになってしまう世界です。そのままでは、利用者様や関係者にご迷惑をおかけしかねません。
正確な法令の知識に基づく反論は、しないといけないのです。
とはいえ、介護保険法は複雑すぎて、現在市販されているテキスト等の中では法令の解釈がまったくありません。
介護保険法の解釈には、行政訴訟の経験が絶対に必要ですが、それを体験している法曹関係者、コンサルタントがほとんどいないのです。
お知らせ5
チャットGTPで鹿児島の新しい顧問先の事業者さんが、団野法律事務所を探したそうです。まさに今困っている点を打ち込んで。ホームページを見てという方は多かったのですが、チャットGPTで探したというのは初めて聞きました。時代ですね。さっそくチャットGTP聞いてみたら、本当に日本1と出てきて驚き! 分析もお得意ですね。





放課後等デイの行政対応テキスト完成。事業所、行政書士など専門士業の先生向けです。放デイは発達障害児対象に各地で利用が増加し、指定を受ける事業者も増えました。一方で行政の指導監督が強化され、自発管など職員不足から人員配置に悩む事業者もあり実地指導、監査対策が急務です。この本は法の支配、法治主義の観点から、行政権力に対抗する方法も提案しました。
目次 テーマ1 どうして政対応が大切なのですか。 テーマ2 行政処分にはどのようなものがありますか。 テーマ3 聴聞手続とはどのようなものですか。 テーマ4 連座制とは何ですか。 テーマ5 法令遵守のためには何をすべきですか。 テーマ6 突然、立入り調査にこられることはありますか。テーマ7 ローカルルールは守らないといけないのですか。その他監査のとき、行政職員が事業所のパソコンを勝手にみることができますか、などなど。
内容についてのお問合せは団野法律事務所0952-29-5036 まで。ご注文はs.remiremi2012@gmail.comまでご連絡ください。
Amazonで電子書籍もご購入できます。
「放デイの知らないではすまされない!」購入サイト